ブログ
ブログ一覧
京都新聞に掲載
10月29日 晴れ
【京都新聞】掲載記事

【本屋の人形展】本日初日を迎えました。
先日、京都新聞に掲載していただき
記事を見て、ご来場くださった皆々様
誠にありがとうございました。
3日まで開催しております。
是非お立ち寄りください。
【本屋の人形展 2025】のご案内
10月19日 曇り
いよいよ“秋”ですねぇ~!!
今月末から6回目となります【本屋の人形展】が開催されますのでご案内申し上げます。
*場所=大垣書店京都本店 イベントスペース催
*日=2025年 10月29日(水)~11月3日(月・祝)
*時=午前11時~午後7時(最終日は午後4時まで)
*アクセス=地下鉄烏丸線四条駅北改札口・阪急京都線烏丸駅26番出口直結
(京都市下京区函谷鉾町78 SUINA室町1F)
*お問合せ=TEL 075-600-2164
(クラフトアート人形コンクール実行委員会)
今年の案内はがきは
人形作家shiroさんの作品です。「鳥獣戯画」より
動物を作れば天下一品!
生き生きとしたその表情にきっと笑みがこぼれるでしょう!!
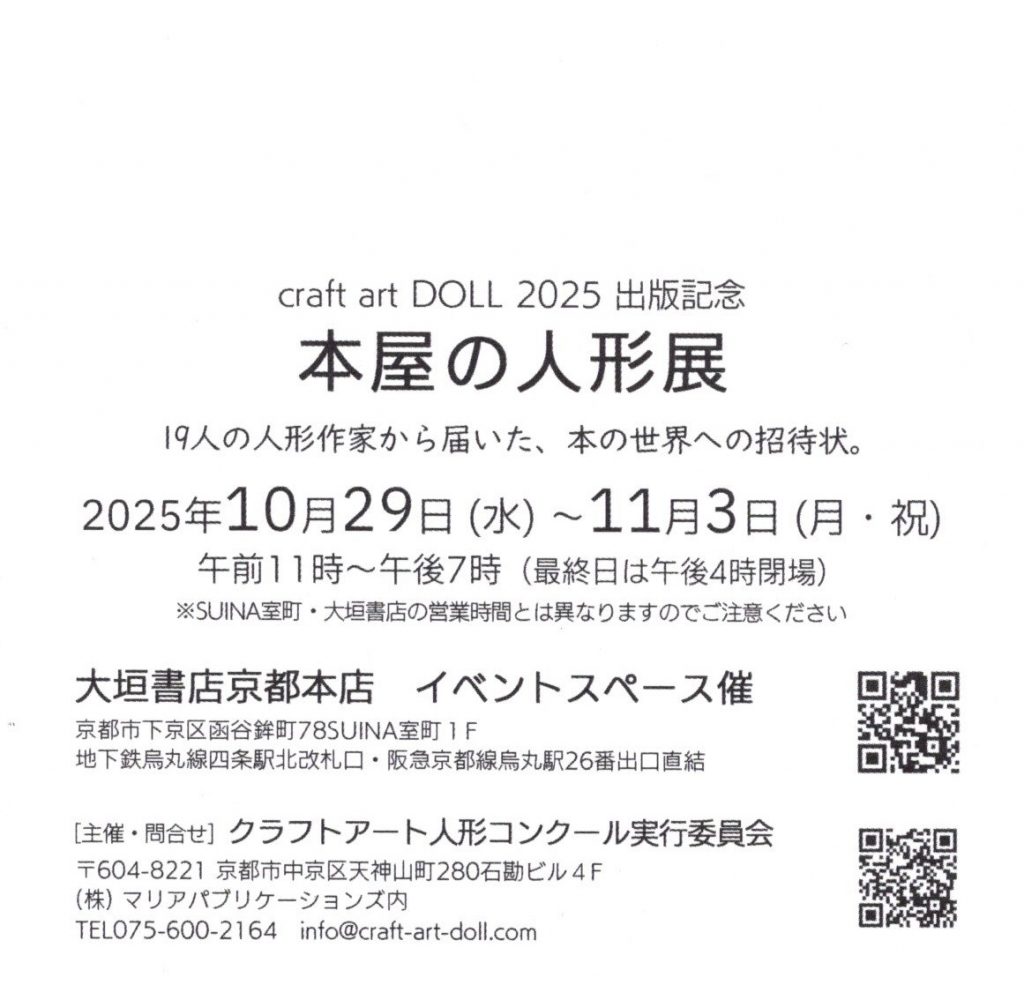
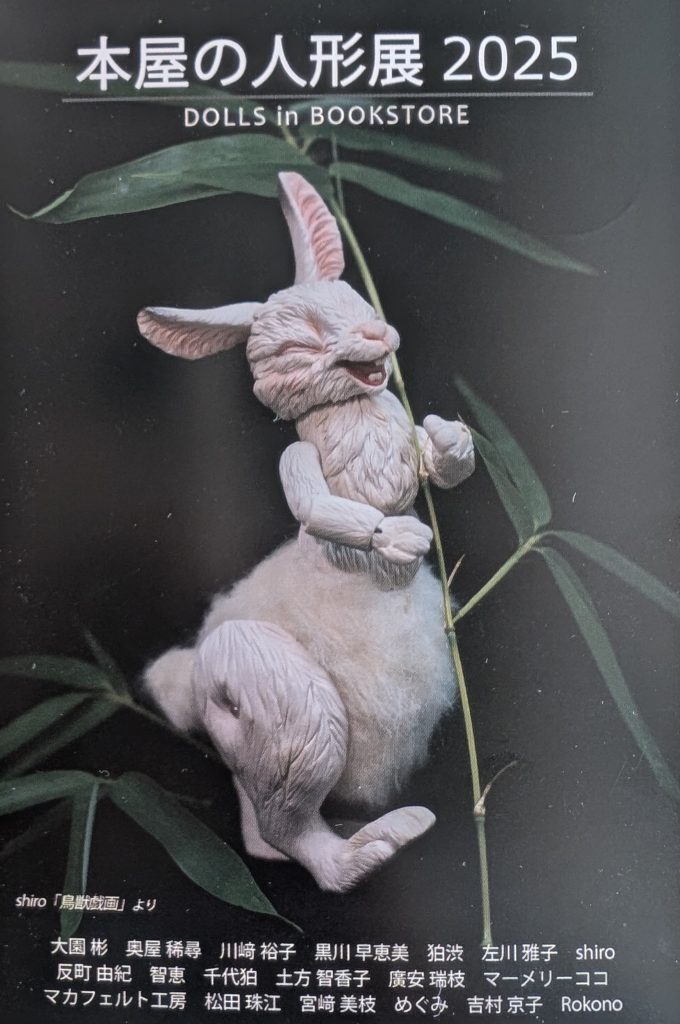
19名の作家が集います。
私は【細川ガラシャ】ビスクドール (85cm)を出展いたします。

どうぞごゆるりとご高覧賜りますようご案内申し上げます。
(初日・最終日在廊致します)
こんにちは、アリスです!
9月14日 曇り
こんにちは!
はじめまして、私「アリス」です。
いろんなポーズが楽しめます。
好奇心がいっぱいのくりくりした青い瞳はガラス製。
靴は本革を使用。
髪は人毛です。
レース飾り付きのスタンドは
お座りの時にも使えてとっても便利。
<全長約47cm>

<どんなポーズもピタッと決まる!!>





お座りもこれでOK!!
さぁ~、「アリス」と一緒に楽しい物語の世界へ!!
ご案内
9月11日 晴れ
日没後、草むらから聞こえる微かな虫の声に
夏の疲れが優しく解きほぐされていくように感じます。
さて・・・お待たせしました。
2025年 日生協カタログ通販
【25好きな暮らし 秋冬号】~~くらしと生協~~
のご案内を申し上げます。
今年の新作ビスクドールは【アリス】です。


<25【好きな暮らし】秋冬号 日生協カタログ誌面 より>
首、手、足首が可動
飾りレースのスタンド付き
お座りだけでなく、どんなポーズも思いのまま
全国の皆様にお会いできるのをとても楽しみにしています。
<さぁ~ 貴女も アリスと一緒にワンダーランドへ❤❤>
鬘(かつら)を作る
8月11日 雨
今回は、戦国時代の髪形に合わせて
オリジナルの“かつら”を作りました。
先ず、かつら店から『みの』を取り寄せます。

『みの』とは、毛束の上部を縫製処理したもの。
主にウィッグ、エクステ等に使用されます。
今回は人毛を使用しました。
予め、頭の形にピッタリ合わせた土台を作ります。
その土台に少しずつ丁寧に貼り付けていきます。
なかなか根気のいる仕事ですが
手順良く、落ち着いてやれば問題ありません。
イメージ通りの髪形に仕上がりました。



<<<装着!!>>>



❤<<<「ガラシャ」 気に入ってくれたかなぁ~?>>>❤